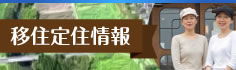ここから本文です。
更新日:2025年9月9日
令和7年第3回定例会
令和7年8月29日に質問通告を公開(「更新日」はデータを上書きした日です)
- 令和7年9月2日:4人(前田議員、前川原議員、宮内議員、木野田議員)
- 令和7年9月3日:7人(竹下議員、川窪議員、久保議員、鈴木議員、松枝議員、下深迫議員、德田議員)
- 令和7年9月4日:6人(宮田議員、久木田議員、植山議員、阿多議員、松下議員、前島議員)
- 令和7年9月5日:3人(塩井川議員、池田議員、山口議員)
前田幸一議員(いっしん会)
1.豪雨災害及び新燃岳噴火に伴う災害対策について
(1)8月8日の豪雨災害は平成5年災害以降の大災害であったが、今後の復旧工事の見込みについて問う。特に国道・県道また、鉄道の状況はどうか。
ア.国道・県道の復旧見込みはどうか。
イ.鉄道についてはどうか。
(2)新燃岳が噴火をして霧島市へ大量の降灰があり、市民生活へ影響があったがその対応策を伺う。
ア.農林業への影響はどのようなことが生じたか。
イ.霧島観光への影響を伺う。霧島地区・丸尾地区それぞれ示されたい。また、風評被害があるが、その対策を示されたい。
ウ.今後、秋の観光シーズンを迎えるにあたり、具体的な対策があるのか示されたい。
前川原正人議員(日本共産党霧島市議団)
1.災害対策と今後の改修見込みについて
(1)今回の豪雨災害は、32年前の8.1災害に匹敵する状況との報告がある。市当局の尽力により早急な対応が行なわれた。全市的に災害が発生する中で、福山地区では準用河川である湊川が氾濫し、車3台が押し流される事態となった。この地域の河川や里道復旧整備について、どう取り組んでいくのか。
(2)福山市民サービスセンターは機能不全となっており、郵便局前の架橋も損壊している。今後の対応策はどのように考えているのか。
(3)自治体合併により地元職員が少なくなり、地理に不慣れのため、災害対応の遅れが発生し機敏な対応ができなかったとの声もある。今回の事例を受けて臨機応変の対応が必要と考えるがどうか。
(4)国分向花地域の手籠川周辺では、内水氾濫により住宅への床上・床下浸水被害が広がった。堆積土砂撤去など、県へ要請すべきと考えるがどうか。
2.公立学校職員の処遇改善について
(1)市内公立学校での教職員は、職務以外の業務で手いっぱいの状況がある。このような中で、教職員の労働基準法が守られているのか。また、本市の場合、余剰時数は、どのような運用をされているのか。
(2)「教職員の働き方改革」を進めていくことが求められているが、一方では、部活の地域展開や民間委託など、長時間労働の解消を天秤にかけられるような議論もある。本来、学校教育や部活などは、「青少年育成と人格形成」に立脚して取り組まれなければならないが、教育長はどのように考えているのか。
3.交通渋滞解消について
(1)第一工科大学付近(桷志田泉健康プール前)は、朝夕の渋滞が発生しており、特に霧島方面への右折車両が多く、不便をきたしている。道路拡幅は大きく改善されたが、渋滞解消のための施策が必要と考えるがどうか。
宮内博議員(日本共産党霧島市議団)
1.豪雨災害対策について
(1)8月8日深夜に発生した大雨は、霧島市でも記録的な豪雨となり、河川の氾濫による河川堤防の決壊、内水が溢れたことによる床上床下浸水被害など、32年ぶりの大災害となった。雨水管理総合計画により進められている日当山排水機場、姫城2号排水機場、東郷排水機場では、どのような問題が明らかになったか。また、今後の対策をどのように考えているか。
(2)西瓜川原排水機場では、配備されている移動式ポンプが稼働できなかった。その理由と対策をどのように考えるか。
(3)松永用水路、妙見地区、嘉例川地区、内地区など、大量の土砂が流入して、出穂期の水不足、民家への土砂流入など農業や市民の日常生活にも多大な影響があるが、その原因は何か。災害発生後の具体策をどのように進めているか。
(4)大規模メガソーラー発電所に起因すると思われる災害への対応は、どのように行われているか。今回の災害を受けて、調整池の再整備を事業者に求めるべきだがどうか。
(5)角之下川、嘉例川など県管理河川でも大きな被害が発生している。県と連携した取組を求めるがどうか。
(6)角之下川の内山田3丁目付近では道路から2m以上冠水している。堆積土砂の撤去、調整池や排水ポンプ場整備、河川の拡幅などの対策を県に求めるべきだがどうか。
(7)被災者の負担軽減策として活用できる国保税や介護保険料、後期高齢者保険料などの減免制度の周知と活用を推進すべきだがどうか。
2.用水路敷管理の改善策について
(1)用水路敷の管理は、地域のボランティア活動で行われているが、高齢化や自治会加入率の低下により、従来の管理体制の改善が求められている。昨年9月議会で提起しているが、この間の議論と対策について問う。
木野田誠議員(霧島市政クラブ)
1.新燃岳噴火による被害状況及び対策等について
(1)農業畜産への被害について
ア.噴火に伴う火山灰による農産物の被害はどの程度あったか。また、その対応はどうしたか。
イ.農産物以外のシイタケ等への被害はどの程度あり、どのような対応をしたか。
ウ.噴火以降、河川の濁りによる用水路の濁り、さらには土石流による濁りが立て続けに発生したが、農業用水の水質については問題はなかったのか。また、今後濁りが発生し、水路等に灰が溜まった場合、灰の除去等はどのように実施するか。
エ.降灰により家畜等への影響はなかったか。また、牧草や水源の汚染はなかったか。
(2)温泉供給事業における被害と対応はどうであったか。
(3)インフラ面の影響として水道の被害とその対応はどうであったか。
(4)新燃岳噴火は数年の間隔で発生しており、「一時的な被害」だけではなく
「長期的な生活・経済への影響」が大きな課題であると言える。人命の安全確保、生活環境の維持、農業・観光など地域経済の被害軽減、長期的な火山活動リスクの管理と大別できるが、これらの課題に対し、長期的な展望に立った対策が必要と思うがどのように考えるか伺う。
2.市主催きりしまフォトコンテストについて
(1)毎年実施されていたきりしまフォトコンテストは、近年、2年に1回の開催となっている。これを毎年開催に戻すことはできないか。
竹下智行議員(いっしん会)
1.豪雨災害について
(1)豪雨災害時における情報伝達と避難体制について
ア.8月8日深夜に発生した豪雨災害において、大雨特別警報や避難情報が、市民に対し、どのように伝達されたのか。また、情報伝達における課題と今後の改善策を問う。
イ.多言語での災害情報提供体制や、SNSなど多様なツールを活用した情報発信の現状と、その効果的な運用体制を問う。
ウ.避難所の開設状況と、避難所における感染症対策やペット同伴避難への対応はどのように行われたのか。今後の避難所運営における改善策を問う。
(2)災害時の連携と地域コミュニティの役割について
ア.今回の豪雨災害における、様々な企業・団体との災害協定に基づく連携について、どのような協力が行われたのか。また、県内広範囲に災害が発生した場合の対応策について、市の見解を問う。
イ.通行止めなどの道路情報の周知方法について、道路情報の一元化(システム化)はできないか。
ウ.防災無線や紙ベースなど、災害情報の伝達手段について、情報を得られる人と得られない人の格差をどう解消していくか。
エ.今回の災害で明らかになった、自治会組織や既存のコミュニティ組織の重要性について、市の認識を問う。自治会組織体制の強化や、既存組織を活用した防災対策を全市的に進めていく考えはあるか。
(3)河川管理と関係機関との検証・情報共有について
ア.個人の所有する土地に繁茂した竹等が隣接する県管理の河川の土手に侵入し通水を妨げる要因となり、市内における数箇所の河川で氾濫したため、土地所有者に対して管理の徹底を県へ要望できないか。
イ.県が管理する河川内に堆積土砂等があることで氾濫が起こる要因について、地域住民の声を取り入れながら河川改修等を県へ要望できないか。
川窪幸治議員(霧島市政クラブ)
1.令和7年8月の豪雨災害について
(1)今回の豪雨災害においては、国道、県道、市道等、交通インフラに大きな影響が出ている。このような中、鉄道においてはJR日豊本線及びJR肥薩線で線路の土台崩壊が発生し、長期的な復旧作業になるとされている。今後の運行再開の見込み等について伺う。
(2)日頃から多くの方々が日常生活や通勤通学、医療機関受診のために利用し、必要不可欠な交通手段であると考える。本市の運行再開に向けた取組について伺う。
久保史睦議員(公明党霧島市議団)
1.水の供給体制の確立と水道管の老朽化対策について
(1)今回の豪雨災害で隼人町においては水道管の破損により断水となり約2万世帯に影響が出た。改めて命を守る水の大切さ、ライフラインの重要性を再認識した所である。そこで水道管の現状と今後の取組について問う。
ア.水道管の法定耐用年数は40年といわれているが、総延長数及び管路経年化率、耐震適合率、管路更新率について、現状と早急に取り組むべき課題及び今後の計画について問う。
イ.配水池や導水管を増設し、断水地域の縮小などリスク減少への対策を推進すべきではないか問う。
2.命と健康を守る熱中症対策について
(1)熱中症による搬送件数について問う。
(2)今回の災害時においてどのような形で熱中症対策に取り組んだか問う。
(3)公教育において運動会、体育祭の実施時期や開催時間帯を見直すべきと考えるが見解を問う。
(4)本年6月より厚生労働省の省令改正に伴い職場における熱中症対策が義務化された。本市の職員に対する取組について問う。
鈴木てるみ議員(公明党霧島市議団)
1.移動弱者対策について
(1)先日の豪雨の際、夜中に避難指示が出ても移動手段が無く、自宅で不安な思いをしながら過ごしていた市民がいた。そこで、スクールバスを災害時の避難行動困難者の移動支援に活用できないか、見解を伺う。
(2)高齢者福祉、障がい者支援、子どもの通学、災害時避難を一体的に捉えた取組は、重層的支援体制整備事業の目的にも合致し、地域の課題解決に寄与すると考える。地域共生型の移動支援モデルとして検討してはどうか。
(3)溝辺町では通学手段の課題から、志望校をあきらめざるを得ない状況もあると聴く。高齢者施設送迎車をスクールバスと兼用できないか、市の見解を伺う。
松枝正浩議員(若獅子会)
1.8月豪雨災害について
(1)8月6日~8月8日明け方までの最大連続雨量は558mm、最大時間雨量で93mmとなっている。様々な諸要因が重なり、結果的に内水氾濫を引き起こしてしまった状況にある。この状況を受け、現在、事業を計画、実施している事業の検証作業も必要となってくることが考えられる。まずは、現状がどうであるのか問います。
ア.県及び市所管河川の改修率は幾らか。
イ.これまでの降水量の基準に適用しない雨量であったと理解しているが、これから市整備の設計基準の適用をどのように考えていくのか。
ウ.内水対策における地域の実情に応じた新たな補助事業創設を積極的に国へ要望すべきと考えるがどうか。
エ.復旧体制で、土木技師の採用前倒しや、他自治体等からの派遣要請は考えていないか。
2.隼人駅周辺整備について
(1)隼人駅周辺は、都市再生整備計画や、土地区画整理事業の導入で、整備推進が図られている。令和5年度より、まちなかウォーカブル推進事業を導入し、都市再生整備計画面積52haと同等の区域面積の設定がなされている。
事業年度は令和7年度までとなっている。そこで問います。
ア.まちなかウォーカブル推進事業を導入した経緯と、事業区域内のまちづくりをどのように考えているか。
イ.隼人駅舎の外観リニューアルや、待合所の活用など、JRへも協力を頂き、市と共同で取組を進めていく考えはないか。
ウ.西口広場における県所有地の取扱いを、どのように考えているか。また県との協議は、どうなっているか。
エ.計画している事業は、設定している年度で完了するか。
下深迫孝二議員(市政会)
1.災害時の簡易給水施設の復旧事業について
(1)現在、簡易給水施設を管理している組合等は幾つあるか。
(2)災害等で甚大な被害が発生したときの対応はどのようになっているか。
(3)簡易給水施設の整備等に係る補助率については、災害時は、特例として全額補助を検討できないか問う。
德田修和議員(きりしま政経研究会)
1.災害廃棄物の対応について
(1)事業系の廃棄物の受入れに制限があったようだが、根拠は何か、柔軟な対応が必要だったのではないか見解を問う。
(2)受入れをしてもらえなかった事業者に対して、廃棄費用の助成は検討できないか問う。
2.敷根清掃センターと霧島市クリーンセンターの被害状況について
(1)今回の豪雨災害での被害状況とごみ処理への影響はどのようであったか問う。
(2)復旧作業の計画と現状を問う。
宮田竜二議員(霧島市政クラブ)
1.霧島市立地適正化計画について
(1)本市でも少子高齢化・人口減少が加速している状況において、医療・福祉施設、商業施設や居住等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする市民が公共交通を使って各施設にアクセスできるなど、本市全体の構造を見直し、コンパクトなまちづくりに取り組むために「霧島市立地適正化計画」がR6年3月に策定された。
ア.同計画に設定された居住誘導区域(50頁)において、8月8日未明の豪雨被害はどうであったか。
イ.同計画で地域拠点と設定された地域の内、溝辺地区と霧島地区は都市計画区域外なので、「地域生活拠点」としても設定されている(同計画54頁)が、横川、牧園、福山地区との違いは何か示していただきたい。
ウ.本計画の誘導施策に公共交通ネットワークの確保(75~76頁)がある。隼人駅東口の供用が開始された際にどのようなネットワークに変化するのか説明を求めたい。
エ.本市周辺の市町も本市以上に人口減少が加速している。事務事業を効率的に共同処理するために、広域連携していく必要があるのではないかと考える。伊佐市、湧水町とで構成する一部事務組合の再編・統合に関する協議会も発足したようである。その状況と今後の見通しについて説明を求めたい。
オ.近年のライフスタイルの多様化に伴い、「二地域居住」に注目が集まっている。本市には空港があり、「二地域居住」に大変優位な環境にあると思われる。移住のように定住人口は増やせなくとも、関係人口を増やしてまちの活性化を図る施策として、促進する考えはないか。
久木田大和議員(きりしま政経研究会)
1.災害時の対応と、今後の災害予防への対策について
(1)8月7日夜から8日にかけての大雨による内水氾濫、河川の決壊が発生したことにより建物等に多くの被害が発生した。
ア.市街地の浸水では市役所やその周辺においても被害が発生しているが、雨水管理総合計画の中でどのように対策をとってきたか。
イ.今後、抜本的な対策が必要と考えるがどうか。
ウ.河川復旧に向けた今後の計画を問う。
エ.小廻地区では上部の砂防が機能していない状況が見られたが、今後、河川の管理等についてどのように考え県に求めていくか。
(2)消防団は明け方に待機指示があり、災害への出動準備を行った。
ア.消防団が待機指示の目的はどのようであったか。
イ.消防団の詰所で、市による情報収集のためのTV、ラジオ等の配備の状況はどのようか。
植山太介議員(無会派)
1.広域連携について
(1)錦江湾奥会議や霧島ジオパーク推進連絡協議会など既存の取組実績はどうか。課題等はあるか。
(2)広域連携には近隣市のみならず、同じ課題や特色をもった自治体と連携をしている地域もあるが、今後の計画などはあるか。
(3)これからの鹿児島県全体を見据え、県央中核都市として、本市の責任・役割をどう捉えているか。
2.隼人港へのクルーズ観光客誘致について
(1)本年8月4日に「隼人港へのクルーズ観光客誘致に向けた勉強会」があったと聞くが、どのような内容であったか。また、今後どのような計画であるか。
阿多己清議員(霧島市政クラブ)
1.郡田川辻松山堰の管理等について
(1)この施設は、平成12~13年に県が整備し、市及び土地改良区が管理している重要な工作物である。25年が経過しているが、設備等の定期的なメンテナンスの必要性についてどのように考えるか。
(2)水量が一定を超えた場合、両ゲートが自動転倒するようになっているが、取水口の門も自動的に下がる仕組みはできないか。
(3)ゲート内に上流からの土砂がかなり堆積し、毎回管理が大変である。抜本的な対策として、地区からも要望されているが、永谷川や松尾川上流の砂防堤内の土砂除去が必要だと思う。県の所管事項であるが、市としての見解はどうか。
2.清水地区の新設道路計画について
(1)消防団清水部詰め所前交差点と国分中学校北東部とを結ぶ道路計画について、県道60号の渋滞緩和にも繋がると思うが、必要性についての見解を問う。
(2)新たな道路整備について、長期的な視野に立って計画していく考えはないか。(令和6年第1回定例会で一般質問あり)
松下太葵議員(若獅子会)
1.観光支援と市街地経済の回復について
(1)被災した旅館・ホテルに対する補助金や融資制度の活用状況、今後の支援方針について問う。
(2)新燃岳や水害の影響による観光客減少を回復させるための、観光誘客キャンペーンの具体策について問う。
(3)被災や客足減少に直面している市街地飲食店に対する応援キャンペーン
(クーポンや商品券事業等)の検討状況について問う。
(4)災害発生後に正確で迅速な観光情報を発信する仕組みづくりについて問う。
(5)観光関連事業者や商店街との協力体制を構築し、復興と地域経済回復を加速させる取組について問う。
2.避難所の在り方と被災者支援について
(1)避難所に駆け込んだ人への水・食料・衣類などの初動物資をどう備蓄・確保するのか問う。
(2)市が指定している避難所ごとの備蓄状況と、その更新・補充の仕組みについて問う。
(3)避難直後から安心して生活できるよう、プライバシー確保や医療・福祉面でのサポートをどう整えるのか問う。
(4)想定を超える避難者が発生した場合に備えた、追加避難所の開設基準や民間施設との連携の必要性について問う。
前島広紀議員(市政会)
1.道路新設改良事業について
(1)国分地区の外環道路の役割を担う重要な路線である(仮称)新町~久保田線の事業について
ア.この計画が考慮された経緯と経過年数を問う。
イ.現在の進捗状況を問う。
ウ.今後の計画について問う。
2.災害発生時の特に高齢者支援について
(1)令和7年8月7日夜遅くから8日明け方にかけての大雨(線状降水帯が発生)は、短時間に水位が上昇し各地で交通が遮断された。このような災害時の高齢者支援について
ア.高齢者に対する情報発信はどのように行われたか問う。
イ.高齢者支援はどのように行われたか問う。
ウ.今後の災害時における高齢者支援の取組について問う。
3.学校施設の老朽化に伴う改修計画について
(1)国分北小の老朽化に伴う改修計画の進捗状況について問う。
塩井川公子議員(若獅子会)
1.丸岡公園のさらなる活用について
(1)霧島連山が一望できるアクセスの良い丸岡公園である。この度、ゴーカートが日本一の長さになり、家族連れの方々が多く来られている中で、さらに年間を通じて利用できるキャンプ場はできないか。
2.横川地区の活性化に向けて
(1)山ケ野金山に高品位の金の鉱化が発見された。山ケ野地区の活性化への道筋ができると感じる。また、国道504号横川横伏敷集落に縄文時代の土器が見つかった。横川地区発展のため、どのように捉えているか。
池田綱雄議員(いっしん会)
1.こども館南側の崖崩れについて
(1)崩落周辺の安全対策を問う。
(2)今後の大雨や台風等で二次災害が心配されるが対策を問う。
(3)崩落側の敷根集落への対応を問う。
(4)安全性が確認されるまでの間は休館にできないか問う。
(5)今回の崩落は木の伐採が原因との声を多く聴くがどのように捉えているか問う。
(6)通行止めが解除されたが安全性は確保されたか問う。
山口仁美議員(いっしん会)
1.国分総合福祉センターの調理室利用について
(1)現在、霧島市国分総合福祉センターの調理室は、成年後見センターとして使用されており、調理室としての利用ができない状況にある。
ア.本来の調理室としての利用について、どのような見解か。
イ.現在、やむを得ず近隣の調理施設を使用せざるを得ない状況にあるが、案内はどのように行っているのか。
ウ.自助具等を活用した調理研修などを希望する声もあるが、近隣にバリアフリーに配慮した調理施設はあるのか。
エ.霧島市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例及び施行規則第5条・第9条では、利用料減免についての定めがある。現在は、利用者が代替施設を利用する場合、その代替施設の条例や規則等に従う必要がある。やむを得ず近隣の調理施設を使用せざるを得ない場合、国分総合福祉センターと同様の減免ができないか。
2.災害時の庁内外の情報伝達手段の拡充について
(1)大雨災害発災当日において、市役所への電話、庁内の内線などが使用しづらい状況や、故障により通話がうまくできない事象が起きた。
ア.原因は何か。今後同様の事案が起きないように、どのような対策を行うか。
イ.音声通話(電話・内線)に頼りすぎない方法の併用を積極的に行えないか。
ウ.市民からの通報・連絡手段を、電話応対以外の方法まで拡充し、音声通話(電話・内線)への負荷を減らすことはできないか。
会議時間の都合により、翌日の質問者を順次繰り上げることがありますので、事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください